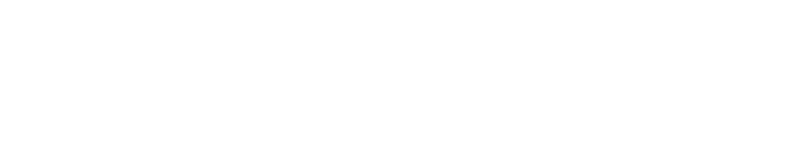テキストで直接読める「防災だより」
| 今までのPDFデータへは、こちらから |
|---|
| 2025年06月号 |
| 2025年06月号の音声読み上げができます。 |
|
『南海トラフ巨大地震』その15「想定の整理」 南海トラフ巨大地震が発生した場合、揺れから始まり何が並行して起こるのかを考え「22分類」しました。 今回は『⑭ 避難所』を考えます。 昨年、NHK連続ドラマ『おむすび』で、阪神・淡路大震災直後の『避難所』の様子が描かれるシーンが放送された。 最近では避難所の劣悪さが少しは改善されたとはいえ、まだまだ途上中の暗中模索の状態が災害の度に繰り返しています。 阪神・淡路大震災が『避難所』という概念が生まれたことは間違いの無い事実です。 さて『避難所に必要だと思うコト』と『避難所に必要だったモノ』とは、乖離していることを知らなければなりません。 言い換えると『備えておいて良かったモノ』と『備えておいた方が良かったモノ』が違うのです。 それらはケースバイケースなのですが、地域によっても違うし、人によっても大きく違います。 NHK連続ドラマ『おむすび』の中では、地震後の人の心底の模様・葛藤を描いていました。 『また明日ね』と別れた昨日の『またね』が再び現れない現実。 避難所は、ただ避難すれば良いだけの場所ではない状態となる現実。 それぞれの事情が違う人達が一カ所に集うことで言い表せない大変さが存在します。 簡単に『避難所運営』とは語られますが、それぞれの人の心に寄り添うことは、とても難しい場所となります。 悲しみや苦しみを理解できるはずもないのです。 多くの『心のボランティア』の方々が、避難所を回られ心のケアをされておられました。 避難所は避難すれば良いだけの場所でもなく、災害をやり過ごすだけの場所でもない。 普段からの付き合いがあってこそ、いち早いケアをコミュニティの中で始めることが可能となるのです。 その為にも普段からコミュニティに何らかのカタチで参加し、少しでも居心地の良い場所を創り上げる努力が必要となります。 『また明日ね』の言葉が実現するように、備えや構えの努力をしておきましょう。 その為に心のモチベーションを維持し、継続可能な防災を育もうということです。 その第一歩となるのが挨拶です。 『おはよう』『こんにちは』『おやすみなさい』『いってきます』『ただいま』等々。 挨拶が紡ぎ育むコミュニティを創っておきましょう。 『避難所』の学びは、現在では「避難所運営ゲーム・HUG」などもあり、学びを通して防災活動をスキルアップ・バージョンアップされていることでしょう。 そこで大切なことは『避難所に避難したら、決してお客様では ないこと』を忘れないようにしましょう。 自分ができることを、自分のできる範囲で無理せず普段していることをお互い様の気持ちを持って行うことが大切です。 そして、忘れてはならないのが『休息・休憩をとること』です。 休息・休憩も仕事の内です。 特に自主防災組織の役員は、頑張りすぎる傾向にある。 戦いは長い!休むこと、眠ることを忘れずに!しかしながら『休息・休憩をとること』『休息・休憩も仕事の内』には賛否両論があります。 避難所運営してきた人からは『休憩・休息をとりたくても取れない』『休憩・休息をとっていると怠けているように思われる』『避難所での生活を知らないから簡単に言える』。 専門組織の方からは『休憩・休息をとらせるのが責任者の努め』『休憩・休息は強制的に行わなければならない』『災害対応時は暴走しやすい』『モチベーション・体力が下がり続けてしまうようでは全員がエラーを起こす』等々。 どちらの意見も貴重な過去の災害後の大切な教訓です。 正しい判断ができず活動が暴走し二次災害が起こらぬようにしなければなりません。 その為にも一人でやるのではなく、複数人でやることが望ましい。 できれば交代制を導入することです。 真夏・猛暑の中での連続作業は注意が必要です。 真冬・極寒の中での連続作業も同じく注意が必要です。 災害は時節・季節・気候を選んでくれません。 だからこそ『正しい司令塔が必要』なのです。 これは普段の日常でもいえることで、司令塔が自分の利益利潤だけを追求する人には、物珍しく耳障りの良い言葉に最初は人が集まれど、徐々に人は離れていきます。 ところが正しい司令塔の場合は、徐々に人が増えていきます。 これらのことを考えると防災活動・地域活動のみならず、日常の社会生活(家庭・会社)でも同じことがいえるでしょう。 その延長線上に『避難所が存在する』のです。 綺麗事では済まないことも多い。 しかし綺麗事も語らなければ、心は私利私欲に進んでしまうのです。 まずは『綺麗事を語り、夢を語り合える仲間を作り、仲間を増やしていきましょう』。 きっと良きコミュニティが構築されるに間違いありません。 そこで避難所の教訓を学びましょう。 避難所運営では成功例も失敗例もあります。 どちらも大変な活動の中で出現する事例ですが、メディアでは大変スムーズにいった事例の紹介は少ないようです。 『大変だった。 難しかった』といったお話がメディアでは取り上げられることが多いように思います。 大前提として『どこの避難所も大変だった』のは間違いのない事実です。 何故、スムーズに迅速に動けた事例を学ぶことが難しいのかといえば、『災害が起こり被災して大変だ!』という表現を伝えるために『スムーズ感は不要だ』と言われた方がいます。 伝え手からすれば、何を伝えたいかによって切り取りも違うのでしょう。 仕方のないことですが、スムーズに活動していると被災状況が伝わりづらい等々、まして活動しているのかが視聴者には理解しにくい(見えにくい)といったこともあるようです。 これは日常的にコミュニティが構築されており、円滑なコミュニティ、理解度 の高いコミュニティ、それぞれの役目が避難所でも普段通りに繰り広げられているからです。 やはり日頃のなせる技なのです。 ここには『理解する・理解できている』ということが根底にあります。 いわば指示系統が上手く機能しているのです。 そこには『指示』はあれど『命令』は無いことも並行して伝えておかなければなりません。 しっかりと『お互い様』が機能しているのです。 避難所は『お互い様で成り立つ基本ルール』これを忘れなければ必ず成功します。 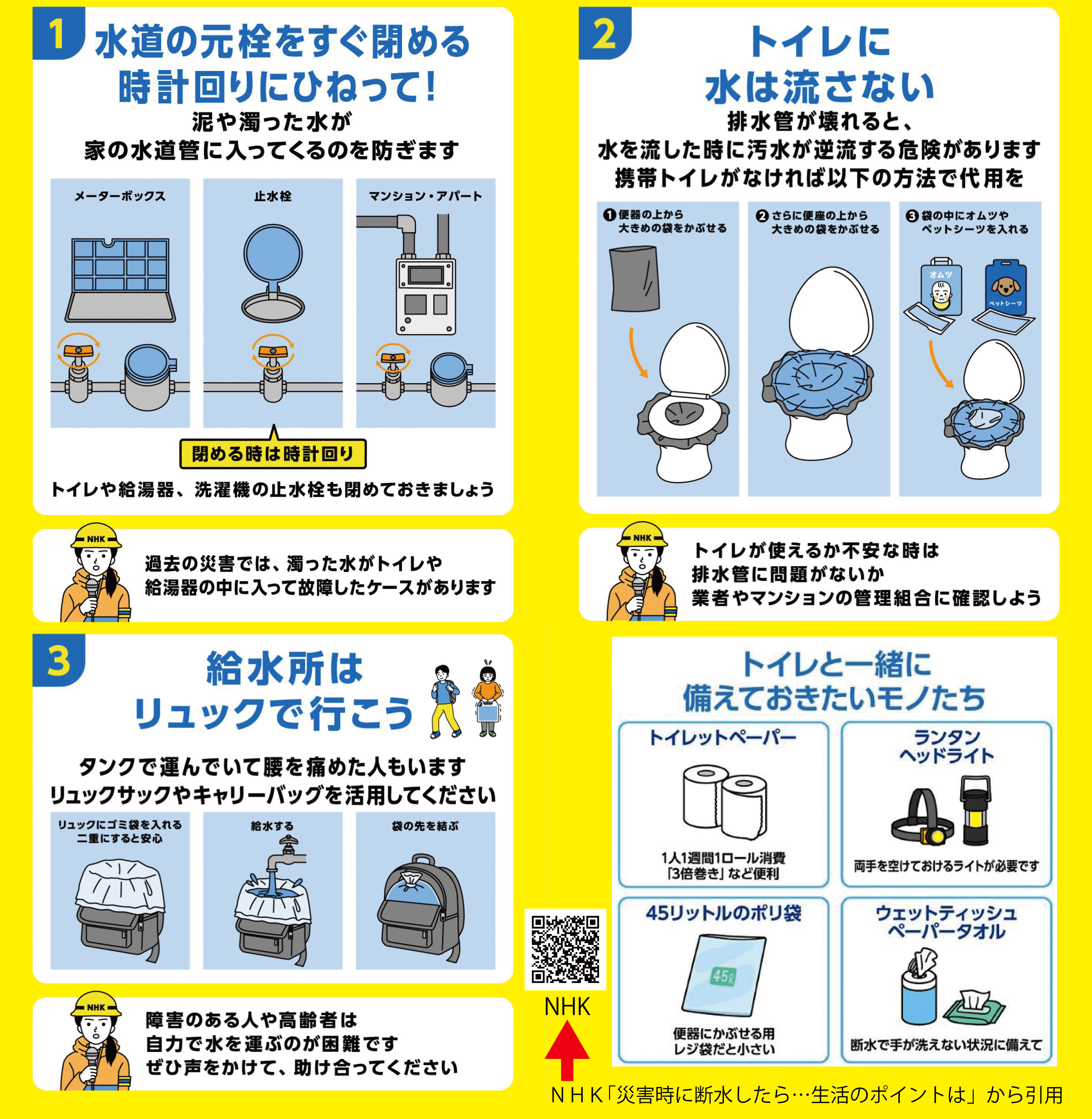 |