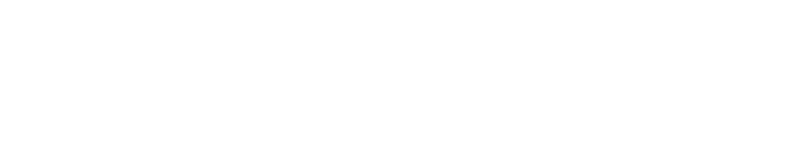テキストで直接読める「防災だより」
| 今までのPDFデータへは、こちらから |
|---|
| 2025年08月号 |
| 2025年08月号の音声読み上げができます。 |
|
『南海トラフ巨大地震・想定の整理』 南海トラフ巨大地震が発生した場合、揺れから始まり何が並行して起こるのかを考え「22分類」しました 今回は『⑮コミュニティ』について考えます 「防災にはコミュニティが必要!」と説かれる方は多い しかし「なぜ防災にコミュニティが必要なのか?」をひと言で答を出せる方は少ないのが現状です 防災にコミュニティが必要なことは、なんとなくぼんやりと知っている方が大半 でも『ひと言で』となるとほんのひとにぎりの人しかいないように感じます 防災にコミュニティが必要なのは『共助の為』ではありません 多くの人は共助を勘違いして『共に助け合うことだ』と思っています 『防災にコミュニティが必要!』と声高にいえども、地域活動やコミュニティ活動に参画していない人が多いのも事実です なぜならコミュニティ活動は綺麗事だけでは済まないことが多いからです また他人からの『ありがとう』といわれる言葉に酔いしれて勘違いした活動「自己満・自分ファースト」になっている場合も見受けます コミュニティ活動は何の為に・誰の為に行うのかを整理する必要があります ここがコミュニティ活動のスタートラインとなるのです コミュニティの根幹には『お互い様』があります しかし『守る側』『守られる側』と分類していては、お互い様を築き上げることはできません お互いが『自分ができることを、自分ができる範囲で、自分で努力すること』が重要です 「私は何もできないから皆さんに助けていただく側」と自分で決めてはいけないのです そこで「自分ができることは何だろう?」と考えることも大切な活動のひとつです 人それぞれできることは違います 違って当たり前 その自分のできることのひとつに『自分は生き残る、生きる努力をする』と決めておくことも重要な『できることのひとつ』です ところが「私はあの世からお迎えが来ればそれでよい」等とマイナスな思考とマイナスな行動をされると、一分一秒が大切なときにマイナスからのスタートとなり、二次被害誘引の原因になりかねません まずは『私は生き残る!』このことはしっかりと心に決めて頂きたいのです そうすればプラスからの動きとなり、助かる確率が飛躍的にアップします まずは『決める・決めておく』これもコミュニティを防災活動に利用できるひとつの近道です なぜコミュニティが防災には必要なのか?「助けてもらえるから」なのか?では誰に助けてもらえるのでし ょうか?「どこかの知らない誰か」では意味がありません 知らない誰かを当てにするのは、雲をつかむような考え方でとても危険です 参加したそのコミュニティの誰か?これでも意味がありません ではコミュニティ参画は誰の為なのか?ここから考える必要があります 「私も助ける側、あなたも助ける側」こんな図式も存在しません そもそも『助ける側、助けられる側』という図式は存在しません 防災のお互い様はそういうことではないのです 自分ひとりの知識量は、いくら知識のある人でもちっぽけなひとりの知識です ところがコミュニティという人の集まりで、1人より2人、2人より3人と多くなればなるほど知識が増えるのです 『コミュニティに参画すれば、シンクタンクが手に入る』ということになります ただ増えれば良いというモノでもありません 正しく楽しく知識を増やすことが重要なのです そうすることで新しい記憶容量が生まれ、知らなかった知識がそれぞれの中で増殖します 『新しいカタチの知識が構築されていく』ということです 更には、世代を超えてお互いが学び合い、知らないことが発生すれば『調べる・学ぶ』ということが育まれることで、それぞれの知識が増えていきます そこで現れた『答』が他のコミュニティと違うかもしれませんが、自分達には必要だと考えた結果の答なら『正しい』ということです またその答は変化してもよいし、新しい要素が加われば、必ず変化することでしょう その変化を、否定してはならないというルールも作っておきましょう ただし、私利私欲・自己中心・自己満足に走らぬように、ルールとマナーは持っておく必要があります なぜ防災にコミュニティが必要かは、そもそも誰の為なのか?地域を守る為なのか?仲間を守る為なのか?この整理をしておかなければ『防災にコミュニティが必要なのか』の答を導き出すことはできません 当然『防災とは自分の大切な人を守ること』という定義は不変の決め事として、その大切な人を守る為には、自分がケガもせず生き残った上で可能となる話です と考えるならば、まずは自分を守ることが最優先事項ではないでしょうか 自分をも守る気もないのに他者を守ることはできません 自分を守る為に何をすれば良いのかを優先的に考えておくべきです 防災を学び、知識を拡充する為に防災を学ぶチームを作り、そのチームが更にメンバーを増やし『お互いを補い合える仲間を増やす』 補い合える仲間ができれば、ひとりではできなかったことが可能になります 自分にスキルが無くても、スキルを持つ人が周囲にいる環境を作ることです そこにはやはり『お互い様』の存在です 自分のシンクタンクができ、その輪が地域を越え『繋がる相手』が増えれば、クラウド上にあるビッグデータが手に入る いわゆる カウンターパートナーの存在です ところがここで大切なルールがあります 『お互いが守り合う』のではなく『お互いに守り合える努力をする』ことです 助けてもらえるのではなく『助け合える努力と学びをする』ことです これはよく聞く『協定』ではありません お互いが自分を守る努力をする繋がりなのです 『協定、協定、これで安心!』 これは大間違い!『協定』をしたからとはいえ「協定先が最優先」とはなりません 学ぶ努力を互いに行い合うことこそが大切なのです 『協定』よりも、共に学び合い、共に生き抜く努力をする仲間を創ることが重要です この努力する仲間こそが、防災コミュニティであり『防災にはコミュニティが必要だ』となるのです さて、防災にコミュニティが必要なのか?の答は『自分の為』ということです 他人を助ける為、町を守る為、瞬時に駆けつける等という正義の味方でもなく、町を守るヒーローでもありません コミュニティの存在は、めぐりめぐって、マワリマワッテ、自分の為なのです その先にある定義『自分の大切な人を守るため』に必要なアイテムです 『防災にはコミュニティが必要』なのは、『人は一人では生きていけない』『どこかで誰かに助けてもらっている』 これを決して忘れてはならないのです 皆様も、なぜ防災にコミュニティが必要なのかを考えてください きっと違う答が生まれるかも知れません 最後に『なぜ防災にコミュニティが必要なのか?』をひと言で答えるならば、『コミュニティは自分と自分の大切な人を守る為のシンクタンク』ということです 災害が発生するまでに学び合う仲間を創るアイテムとして、皆さんも防災活動に参加しましょう 正解は「③」 家にいて大地震が来たら『ろうかに逃げる』 地震の揺れはすさまじく、様々な物が動いたり、落ちたり、倒れたりします キッチンやリビングは、食器棚やガラスの破片などが飛散したら危ないものだらけです なので、地震の時はろうかのような「周りにものがない場所」へ逃げ、揺れがおさまるのを待ちます これがいわゆる「自宅の中の安全地帯(シェルター)」であり、日頃から物が倒れてこない、落ちてこない場所を作り、直ちに避難できる動線を作っておきましょう ちなみに、よくテーブルの下にもぐれ(①)と教わりますが、じつは床に固定されていないテーブルは地震の時に動いて凶器になることもあります またテーブル上の食器が落ちてくることもあります ②のように震度も気になりますが、命を守ることが最優先です 揺れがおさまってから地震情報は確認しましょう  |