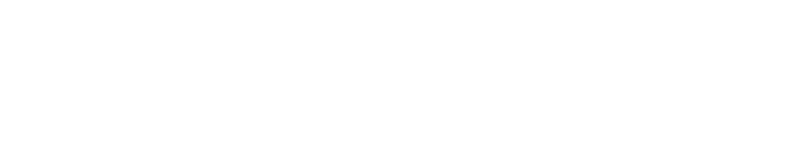テキストで直接読める「防災だより」
| 今までのPDFデータへは、こちらから |
|---|
| 2025年09月号 |
| 2025年09月号の音声読み上げができます。 |
|
『南海トラフ巨大地震・想定の整理』 南海トラフ巨大地震が発生した場合、揺れから始まり何が並行して起こるのかを考え「22分類」しました。 今回は『⑯行政』について考えます。 災害前の行政、災害時の行政、災害後の行政。 ここで言う『行政』とは『防災行政』のことであることを前置きしてお話しを始めます。 まずは災害対策基本法を読まれたことがありますか?国・県・市と分けて、それぞれに責務があります。 国は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。 都道府県は、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、その区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。 それぞれに責務の違いがあります。 これをゴチャマゼにして行政がどうだ、国が、県が、市が、と同一並列に語られることがあるが、それぞれに違う。 簡単に言えば、国は防災に関し万全の措置を講ずる責務。 都道府県は防災に関する事務又は業務の実施を助け総合調整を行う責務。 市町村は防災に関する計画を作成し法令に基づきこれを実施する責務。 やはり『万全の措置を講ずる』のは国なのだ。 その『万全の措置を講ずる責務』と掲げる国に、防災の法律、事前防災の法律、これらが存在しないばかりか、防災に特化した『省庁』という専門部署が、この国に存在しないのは御存知の通り。 災害前、災害時、災害後。 それぞれの行政がある。 しかしながら行政も市民と同じフィールドに存在することを忘れてはならない。 災害対応・防災活動において、他者に丸投げのように、すべて行政がやってくれ るものという考え方は好きではない。 なぜならば、災害がひとたび発生すれば、行政も『同じ被災者』なのだ。 同じ被災者になる人を『災害発生前から当てにする』のは如何なものだろうかと考えます。 イヤな言い方をすれば一般市民が『俺達は被災者だ。 何とかするのが行政だろう!』とまくしたてるのは絶対に違う。 市民も行政も同じ被災者であることを忘れず、共に支え合い、お互いが『できることを考え、できる範囲で心を込めてやること』が重要。 人それぞれできること、できる範囲が違います。 『できることを考え、それぞれがやる』のと、『誰かがやってくれるので自分は何もやらない』のとでは、防災活動・災害対策、地域づくり等々は、まったく違うモノができあがってしまう。 以前にNHKプロジェクトXで放送された『三陸鉄道』。 地震で壊れた路線を鉄道会社や建設会社だけが再建したのではなく、地域住民が自分のできることを自分のできる範囲で一生懸命に今を生きる人達の為だけにではなく、まだ見ぬ次世代の人へ繋ぐ為に自分ができることを考え、自分のできる範囲で、私利私欲なく『地域の為』に動かれたことを描き出されたことを思い出します。 『行政』は、行政の職員や議員の方々、一部の住民が創り上げるのではなく、地域住民がみんなで支え合い創造することで、より良い行政ができあがります。 誰かがやればよいとか、私はやらなくてもよいではなく、誰もが自分のできることを考えてやることが大切なのです。 その為にも自分の住む地域活動に関わり、自分の住みやすい、自分が誇れるまちづくりをしよう。 その為にまずは『自分のまちを好きになること』です。 災害後に『行政』この存在なくして、復興の速度は加速しないと考えられ、更には地域住民の活動を支える重要な役割があるのも紛れもない事実です。 大災害が発生したとき、即活動するのは地域住民であり、近隣の人達であることは間違いありません。 次に行政が動き始めますが、行政の職員も被災者であることが多いのです。 不安がる家族を残して仕事に出ている人は過去の教訓からも多いと考えられます。 そこで同時に動くのは、他所からのボランティアです。 ボランティアもこの30年で進化しました。 自己完結型に徹底されたチームができています。 ここには素晴らしい主導者・指導者の方々のおかげです。 ところが進化がないのは、そのボランティアへの下支えする資金が問題となる。 そこで発動するのは行政のチカラ。 助成金・補助金等々を適切な団体や企業へ支援する。 行政のチカラは『税金』によるものが大きい。 その税を支えるのは『人』のチカラであることは間違いない。 近年「自助・共助・公助」と語られることが多い。 それらの関係性・連結性を説明するのに良い言葉が目にとまった。 『Association』サッカーを見ていて、この言葉が飛び込んできた。 訳せば、連合すること、合同・共同・提携・関連・協会・社団・会社・交際・付き合い等々。 これはサッカーだけではなく、スポーツ全般、地域活動・防災活動でも同じことがいえます。 『共助』も大切だがAssociation『共同』が重要だということです。 それぞれに役目があり、守備・攻撃。 一人が瞬時に判断し、どちらかに変化して行動に移す。 『守備は守備だけ』『攻撃は攻撃だけ』ではないのです。 たとえ守備役でも瞬時に攻撃へ、その逆に攻撃役でも瞬時に守備に変化します。 誰かが事前に決められた何かをやれば良いというものではない。 誰もが何かをやるのです!『私は助ける側』『私は助けてもらう側』この構図ではないということです。 災害や悪しき者は、巧みに変化しニコニコしながら近寄って来ます。 そして弱者の懐に手を突っ込み『大切なモノを奪う』。 自分の大切なモノを奪われないために危機管理という『防災活動』をするのです。 それは大切なモノを奪われてからの事後処理では遅い。 そのことに気が付く必要があります。 そこで『Association』。 お互いにかばい合い、お互いに助け合い、お互いに守り合う、この共同が必要です。 この共同は、同じ立場・同じ目線『同じ』が重要です。 地域もこの『同じ』が基盤になり『お互い様』が生まれます。 『共同』一人よりも二人以上で考え行動すること。 『共助』も大切ですが、『共同』の重要性を考えてみましょう。 そうすると『行政』を運営するのは誰なのかが見えてくるだけではなく、マンションでの地域活動や管理組合活動も同じだということに気が付きます。 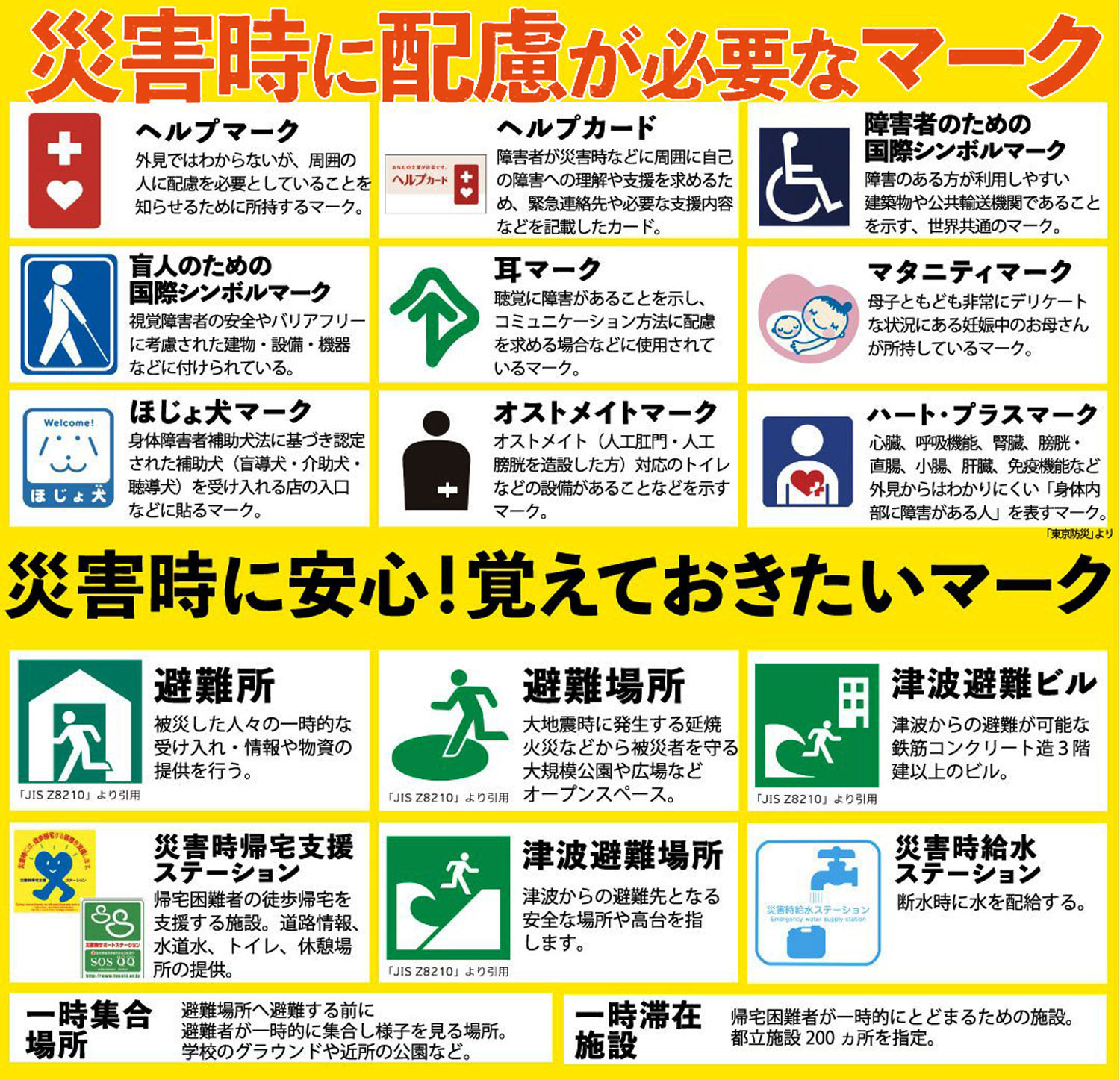 |