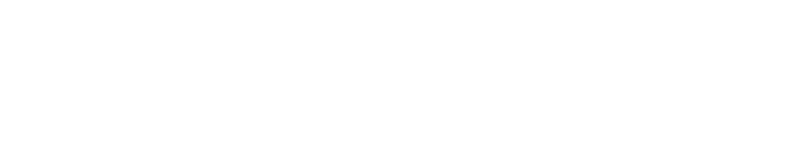テキストで直接読める「防災だより」
| 今までのPDFデータへは、こちらから |
|---|
| 2025年10月号 |
| 2025年10月号の音声読み上げができます。 |
|
『南海トラフ巨大地震・想定の整理』 南海トラフ巨大地震が発生した場合、揺れから始まり何が並行して起こるのかを考え「22分類」しました。 今回は『⑰支援やボランティア』を考えます。 支援とボランティアは違います。 支援とは『ささえ助けること。 援助すること』。 いわば後方から活動等に対する協力のこと。 ボランティアとは、最前線で被災者に寄り添うカタチで、なおかつ被災者が必要とすることをお手伝いすること。 ところがボランティアだけでは長期間にわたりお手伝いするのは、かなり無理がある。 資金、資材、自分たちの寝食もボランティアの人達の懐からでは無理がありすぎる。 そこで支援があると物事は大きく変化する。 継続可能になるのだ。 しかしながら『時間』だけは支援では問題解決できない。 仕事を休んだり、学業を休んでボランティアにあたる。 そこへの支援は『企業や教育機関の理解度』によることになる。 その理解度とは『もしも自分のところが被災すればどうか?』という理解度だ。 ところが日本は遅れている。 支援者へもボランティア参加者へも理解度が低い。 日本の悪しき文化なのだろうか。 最前線に行く者に後方からの支援を皆で理解することが大切であり『行政・市民・企業・組織・ボランティア』が等間隔で補い合うことが理想なのです。 「どこかの知らない誰かがやれば良い」これでは防災力はアップしないばかりか継続力もない。 近年、クラウドファンド・寄付金・ふるさと納税等で支援のカタチも変化している。 誰もが『やる気』を出せば、どんなカタチでも参加できる時代。 自分が思う『できるカタチ』の支援の輪に入りましょう。 こんな風にいうと『余った金は無い』『余分な時間は無い』等々を仰る方がいる。 『もしも自分が?』と考えたなら『余った』等という言葉は心の中からも口からも出ないはず。 防災は自分事と考えることから始める必要があります。 自分事ととらえることが支援やボランティアの始まり。 しかし『忙しくて、防災なんて時間が無い』と仰る方が多い。 でも時間はどの人にも平等・公平に24時間365日与えられている。 この使い方をどのように配分できるかに差が現れるのです。 そこに防災を組み込むことは「むずかしいなぁ?」と思う人も多い。 なぜそう思うのか?『経験値が加算されていないから』と考えられる。 一度でもやったことは『その程度なら』と簡単に思えることと『それは大変だ!』と難しく思 えることがある。 この2つの共通点は『必要な時間がある程度判っている』という事実だ。 どちらも『やったことはある』のだ。 ところが『やったことがない』となると、必要な時間はまったく判らない。 だから手を付けないのだと考えられる。 でも、やる必要に迫られるその時は必ず来る。 被災もしくは災害因発生の時だ。 だが、この時になってからでは事後処理対応しかできない。 多くの人がここで思うことは『事前にやっておけば良かったなぁ』と思うようだ。 なぜそう思うのか、やっておけば、その後の展開が変わったことを知っているからなのです。 多くの人は『知っている』のです。 ところがやっておけばその後の展開の違いを理解していれば、間違いなくやっていたと考えられます。 でも、人はどうしても心のどこかに、正常性バイアスが働き過ぎて『大丈夫、何とかなる』と心の中で現実逃避を図る人が多い。 そのひとつに、次のような言葉を多くの人は使う『ピンチはチャンスだ!』『ピンチをチャンスに変えろ!』となぜだか突如としてポジティブ思考に姿を変えて現れます。 私はいつも次のように考える。 『ピンチは何処まで行ってもピンチだ』『ピンチはチャンスに変わらない』。 正しくは『ピンチを回避できてこそ、その後の動きは変わる。 』チャンスのタイミング、チャンスの時期、チャンスそのもののカタチ、これらを知っていた上で初めて『チャンスは到来する』と考えられる。 ピンチとチャンスはフェーズ(局面・場面)が違う。 ピンチのステージをクリアできてこそ、チャンスのステージに進入できる!なので、自分にできる範囲の何らかの支援やボランティアを経験し、その経験値を加算することで『時間を上手く使うスキルが手に入る』と考えられます。 だがやらなければ、このスキルを手に入れることはできないのです! あなたにできること、自分ができることを始めてみることが防災への一歩となります。 焦らず、慌てず、今!やっておくこと考えることで必ずピンチの後の展開が変わります。 何からでも良い、あなたが興味を持てそうなことから始めてみることです。 次に『⑱お互い様や助け合い』を考えてみましょう。 先の『支援やボランティア』よりも身近な存在である『お互い様や助け合い』『ご近所さん』の存在。 過去の災害後にはこの『ご近所さん』の繋がりが命運を分けた話を多く聞きます。 災害直後、顔が見えない、必ず居るはずなのに、旅行にも行っていないはず、今日は出掛けていないはずという個人情報を共有できている、このチカラが大きかったといえる事案が多くあります。 それは お互い様であり、何かあれば助け合いなのです。 近すぎず、遠からず、適切な距離で『地域の繋がりがある』。 この距離は『直ちに!』と活動できる支援活動者です。 救助隊よりも、ボランティアよりも、行政支援よりも『命を守る15分に間に合う人達だ!』。 過去の災害後の教訓から15分以内の救出は命を守ることができる時間帯です。 72時間とはいわれるが、やはり事実として『15分以内の活動』が明暗を分けています。 声高に『安否確認・個別避難計画』と語られるが、15分以内の安否確認は何件まで可能なのか? 玄関でインターホンを鳴らし「はい」と出てくるまでに何分?更には玄関を開けてくれるまでに何分掛かるのか?そう考えると、多くて3~4件ではないだろうか。 ならば、救助隊はあなたの支援までに何分かかり、行政支援活動は何分後となるかは途方もない数字となる。 やはり『ご近所さんのお互い様や助け合い』ここにもう少し注力・スポットを当ててみましょう。 そうすれば『なぜ防災にはコミュニティが必要なのか?』も見えてくるはずです。 また、お互い様や助け合いの輪は、広げるものではなく広がるものなのです。 こと更に声高に啓発するも のでもなく、自然な繋がりが実を結ぶものなのです。 そこには「あわよくば」と、したたかに繋がるものではなく、計算高く、はかり事をするものでもありません。 あるとするなら『心』なのでしょう。 考えて動くのではなく、自らすすんで動いてしまう。 そんなものなのでしょう。 本来『考えてから動く』方がエラーは少ないはずですが『何も考えず動いた』となるのは『思考』よりも先に『心』が反応したからでしょう。 過去の災害後の教訓の中には『気が付けば動いていた』と語る人も多い。 でも私は思います。 きっと『助けたい!』という感情が最優先で反応し、人を集め、人が集まり、人を助けた。 終わってから『あれ、危なかったよね』となっている。 確かに「ブレーキを掛ける人も多い」。 ブレーキも必要だが『助けたい!助けるぞ!』という『感情』が人を助けたとも考えられます。 きっとそこには『お互い様や助け合い』が心や身体に染み付いた人達なのでしょう。 やらないよりは「やって批判を浴びよう!」目の前で命の灯火は消したくない『お互い様や助け合い』は言葉にならない、カタチにできないものではないだろうか?だから『防災にコミュニティが必要』をひと言で表現できないものなのです。 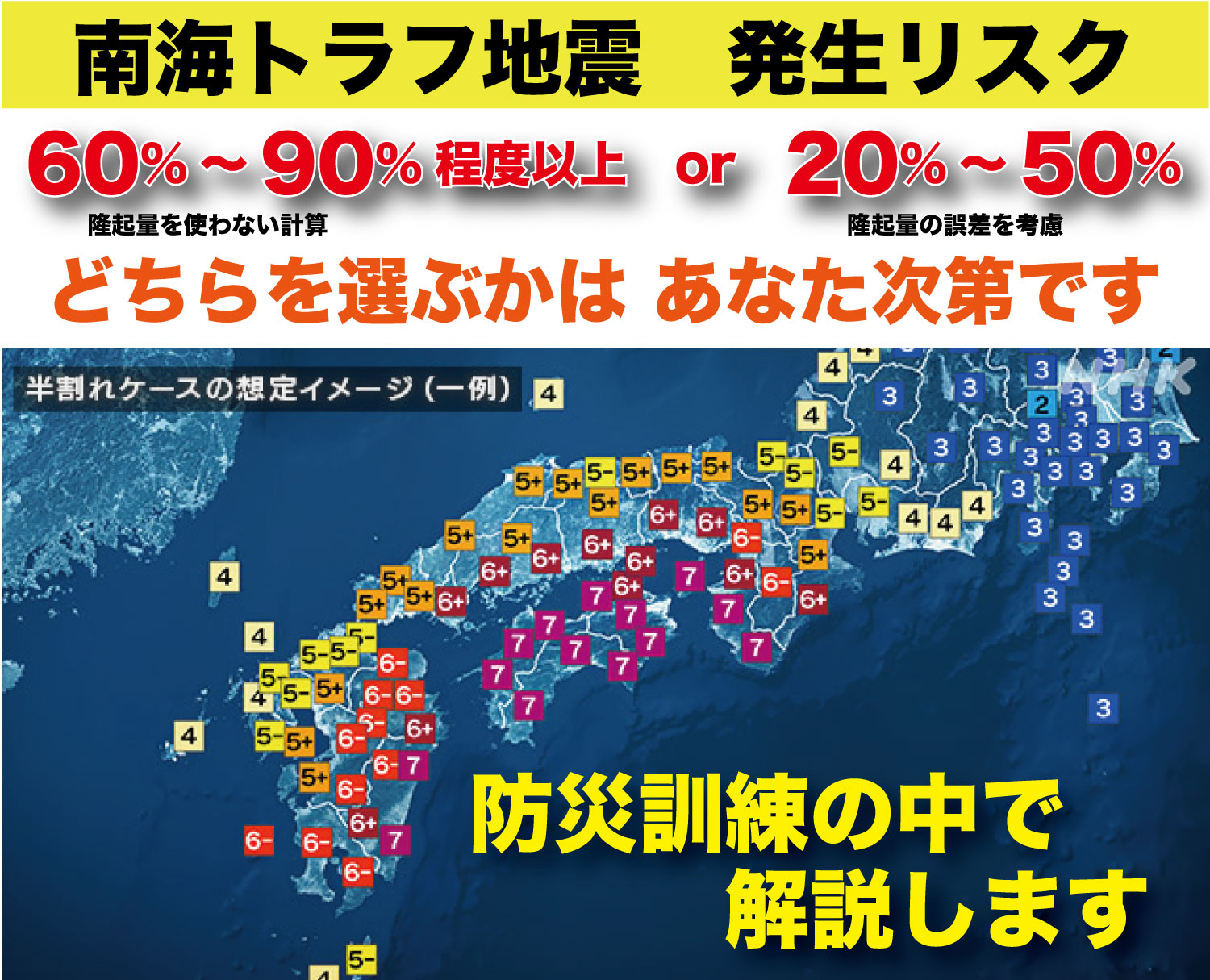 |